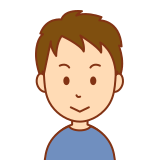
レガシー(古い技術)なWeb制作会社に入ってしまった。。
このままでエンジニアとしていいのか焦る…。
辞めるまでにできる仕事中スキルアップできないかな…。
という人に向けて上記のようなハズレWeb制作会社に入ってしまった場合の解決策を書いていきます。この記事を読むことで辞めるまでにすべきことがわかります。
Web制作会社だけではなく自社開発企業にも当てはまりますので宜しければ読み進めください。
ハズレ会社に入ってしまったら?
あなたの会社はこんなWeb制作会社ではないですか?
- コピペ作業(簡単な更新作業)で1日が終わる。
- いい案件を回してもらえない。
- 先輩もレガシー技術をつかっている。
正に自分もこういった経験、時期がありまして悶々としていたことがあります。
具体的には下記です。
- 入社して1か月ほど案件を振られなかった
- 定期的な運用ばかり
こういった場合結論から言ってしまうと解決策としては2つあり、一つ目は「転職」です。
理由は主に2点挙げられます。
- エンジニアにとって技術の停滞は死を意味する
- 会社を変えるより環境を変えたほうがはるかに効率的
死というのは結構ショッキングな単語ではあるのですが、自分の経験上感じることです。
例えばもしあなたが、その会社で定年までコピペ作業を続けると言うなら問題ないですが、会社を辞めてしまった時詰みます。
- ずっとそれをやっていたいか?
- この会社がつぶれることはないのか?
- 何らかの理由で会社を辞めたくなる理由はないか?
- AIに置き換わるんじゃないか
を考えれば、技術の停滞(特に低い水準であれば尚更)がエンジニアとして生きていないようなものだ、またほかの場所で生きれないということは理解いただけると思います。
すぐは転職できない
とはいえ、
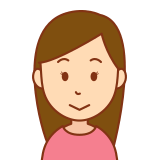
2〜3ヶ月しか働いてないから辞めづらい、次の転職に響きそう
と心配されるかもしれませんが、実際辞めづらい状況であれ、辞めることはなんら問題ありません。
のど元過ぎれば熱さ忘れるという感じで、言うときは確かに気まずいのですが、それは何か月、何年働こうが一緒です。契約社員等でもない限り、退職願は相手からすればいつだって突然なのでその気まずさは諦めましょう。
「次の転職に響く」は多少あり
結論として1年は会社にいた方がいいというのが自分の経験則から言えることです。
2〜3ヶ月で辞めることも問題ないですが、Web業界の面接官でさえ早い退職に対して風当たりが強くなるというのは往々にしてあります。
つまり実際に早く辞めるのが問題というよりは、それを問題視している面接官は一定数います。
なぜなら、辞めた理由よりも実績や経験でその人の評価をしてしまうからです。
つまり、
早く辞めた=
- 元の会社での技術を何も身につけてない
- 嫌なことがあったらやめてしまう
のではないか?
という不安をもたれてしまいます。
その為に書類が通らなかったりするのは避けたいですよね。
企業からすると早く辞められるのは大きな損失なため、出来れば長くいてもらいたいので早く辞める人を入れたくないという心情になります。
以上のことから暇な環境であれ1年は続けた方がいいと思っています。
しかしこれはすべての人に当てはまるわけではないです。
パワハラや精神的負担が大きければ早く辞めてしまっていいですし、技術力に自信があればフリーランスになってしまうという道もあります。
暇でレガシーな環境を打破するための解決策、一つ目は「転職」と書きました。
では2つ目の解決策が何かというと、そういった環境にいつつもスキルアップする方法です。
そうすれば転職までの1年を務めたという実績もありつつスキルアップできますね。
暇でレガシーな環境でスキルアップする方法とは?
1年間、暇でレガシーな環境で
- どうやってスキルアップしたらいいか
- 仕事中の時間を有効活用するか
を解説します。
以下は、危険度が少ない順です。
- 社内営業
- 勉強会
- 情報収集
- ツール作成
- 勉強
- ブログ(アウトプット)
- ポートフォリオ(アウトプット)
- 転職サイト閲覧
勉強までは普通に仕事中でもできると思いますが、ブログくらいから危険度はぐっとあがっていきます。
一ずつと補足していきます。
社内営業
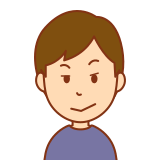
いきなりそんなことさせんの?
ここでいう社内営業は、「何か仕事ないですか~」というアレです。
社内営業という言葉は、好きじゃないですが自分の利を考えてするのが大事です。
つまり雑用目的で何か仕事ないかを聞くのではなく(そんなことするくらいなら早く帰りましょう)、自らスキルアップできる案件をやりたい、挑戦させてほしいとリーダーに伝えることが重要です。
つまり、まずは社内での自分の周囲の環境を変えていけるかを考えてみます。
自分次第で社内環境が変えられそうでしたら是非動いてみてください。
勉強会を主宰する
自分は結構発案するのが好きだったので、過去には以下の勉強会を開きました。
コードスプリント HTML・CSS編
こちらはLIGの記事を見て始めました。

簡単に内容を説明すると、お題担当者が何らかのデザインをモジュール単位(見出しなど)でキャプチャをして、それをお題とします。
お題担当者も含めチームメンバー全員(多くても5名くらいがよさそう)で時間を決めてコーディングする。
この勉強会では、他の人がどんなマークアップやスタイリングをしているかわかってとても勉強になるのでおススメです。
コードスプリント JS編
こちらもお題を出して、それに対してJSを書いていきます。
例:1~100までの数字の中で、3の倍数と3が含まれている数字をconsoleで表示させてください。
答えは下記記事にしています。

この方法で自分も含めチームの士気も高めることができます。
この勉強会何がいいかというと全員が主役になれるということです。一方、講師が一人いて、他の人が受け身で聞くスタイルの勉強会は、講師が一番勉強になり、受け身で学んだ人は身になっていません。
そのため、上記の勉強会でなくとも参加者が全員主体となる上記のような勉強会はおすすめです。
先ほど「会社を変えるより環境を変えたほうがはるかに効率的」と書きましたが、このような勉強会ができるのはある程度メンバーがついて来てくれる、乗っかってくれる土壌がないと難しいため、難易度は低くはないです。
ですが、提案してみるだけでも違うのでよろしければ検討してみてください。
情報収集
こちらは割と皆さん暇なときはやっているかなと思います。
情報収集はfeedlyがおすすめなのでよければ下記記事を参照ください。
プログラミングの情報収集はfeedlyがおすすめ | 登録の仕方と活用術
また情報を自分の中だけでため込むのもいいですが、最新情報を共有し合うというのもチーム活性化につながるのでおすすめです。
ツール作成
自分の話になりますが、始業時間の30分前に出社し、始業時間までは絶対会社の仕事はやらずツールを毎日作るというのを1~2年くらいやってました。
本当に簡単なものや、いつ使うの?というものから、社内メンバーに共有して使ってもらえるようなものまでいろいろ作りました。
例
- cssジェネレーター
- ブックマークレット各種
- chromeアドオン
などです。
社内メンバーに共有して使ってもらえるようなものとしてはBacklogのAPIを利用した投稿・申請ツールなどです。
ちなみに先日Tweetした簡単な「老後までの毎年貯蓄試算」ツールをつくりました。
これもそんな感覚で作ってます。
ツール作りました😃
🔽老後までの毎年貯蓄試算https://t.co/XFUGDF68nk
Vue.jsで簡単な試算ツール作りました!老後2000万円不足するらしいので、今の年齢と貯金を入れると毎月と毎年でいくらずつ貯金しなきゃいけないかわかります。
やってみてわかりましたが、結構2000万までのハードル高いです。。— hoshi (@funclur_01) June 10, 2019
上記までのことは、転職を見据えつつ、社内環境を良くさせる方法でした。
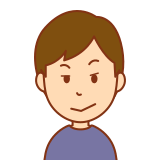
そんなことしたくないし
と思われる方も多いかもしれませんが、割とこういう社内環境を改善させれば面接時アピールできますし、面接官にも受けがいいので、可能でしたらやってみましょう。
ここからは社内環境なんて考えず、自分だけスキルアップする方法になります。
勉強
勉強会とは違って、個人的な勉強ですね。具体的には次の転職のための勉強です。
何で勉強するかと言えば最近いいと思ってるのはkindle(電子書籍)ですね。
なぜなら本より勉強してる感が出ないからです。PC上で完結できるので仕事をしてるふりして勉強できますね。
ただビュアーが細長かったり思ってたものと違うということもありますので、お試し読みしてからgetするといいです。
もちろんネットの中だけで情報をあさりつつ勉強してもいいのですが、1冊やると網羅的に学習できるのでいいかなと思います。
何の勉強するかはそれぞれに応じて変わってきますが、フロントエンドであればJSフレームワークは今後も避けて通れないのでやっておいて損はないです。
主にはVue.jsとReactですが、Vueのほうが敷居が低いのでお勧めです。
ブログ(アウトプット)
Qiitaやブログへのアウトプットは、のちに自分を救うことにもなるのでやっておくべきです。
投稿する記事の基準としては、「その日検索したこと」もしくは「壁にぶちあたって解決したこと」がおすすめです。
「その日検索したこと」については、検索したこと=わからないorまだ定着していないのでブログに書いておけば、また検索するときに自分のブログを閲覧すればいいですね。
また、壁にぶち当たったときも同じくまた壁にぶち当たってどうしたんだっけ?となるのを防げますし、別な人もぶち当たるのでアクセスも集められます。
検索したことは、ありがたいことに検索履歴として一覧化されているので便利ですね。
ポートフォリオ(アウトプット)
ポートフォリオは何も転職で使うためのものだけでなく、自分が身に着けたスキルをアウトプットする場としても使えます。
(もし上司先輩にバレたらアウトプットですと伝えましょう…)
そうしてるうちに転職でも使えるポートフォリオが出来上がるので一石二鳥ですね。
転職サイト閲覧
これは危険度MAXなので、社内での閲覧はおすすめはしません。。家で見てみましょう。
まだ転職しないから転職サイトやエージェント登録はまだいいやと思うかもしれませんが、決してそんなことはないです。
転職サイトは見ておくべき理由として、在職中であっても下記のようなメリットがあります。
・どんな会社があるかがわかる→自分が行きたい会社が具体化できる
・今どんな分野、技術、言語が求められてるかわかる→これから何を学習すればいいかが分かる
控えめに言って一つ一つのメリットがでかいです。
フロントエンドの流れは速いので自分は半年おきくらいに見てました。
とはいえ最近はJSフレームワーク、Node.js、TypeScriptあたりで落ち着いてそうです。
Web専門の転職エージェントは下記です。
まとめ
少々長い記事になりましたが、自分の経験もあり思い入れが強くなりました。同じように暇だな~このままで大丈夫かな~と感じてる人がいたら参考にしてみていただければ幸いです。
以下、この記事のまとめです。
暇でレガシーなWeb制作会社に入ってしまったら
- 社内の環境を変える
- 職場環境を変える
社内の環境を変えるために必要なこと
- 社内営業
- 勉強会を主宰する
- 社内ツールの作成
職場環境を変えるために必要なこと
- 勉強
- ブログ(アウトプット)
- ポートフォリオ(アウトプット)
- 転職サイト閲覧
以上です。
転職するまでの間、暇でレガシーな環境でも、以上のことを実践するとスキルアップにつながりますので、よかったら参考にしてみてください。
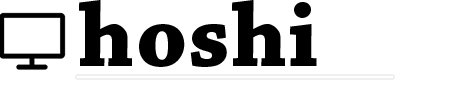



コメント